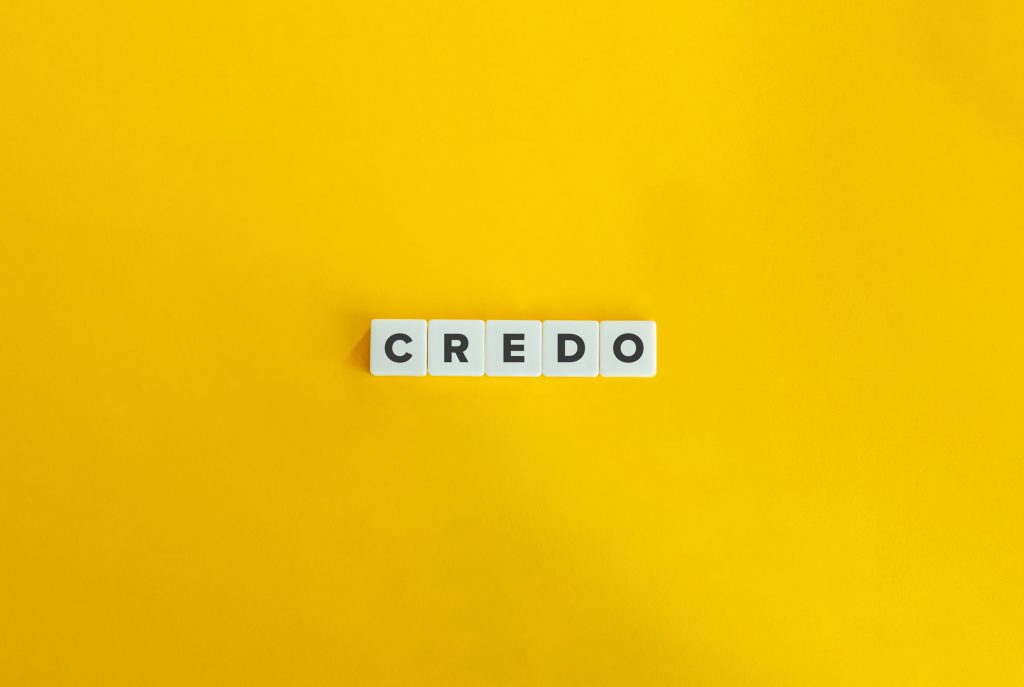
クレドとは何か?
住宅業界は今、かつてない競争の時代に突入しています。人口減少、建築コストの高騰、ネットによる情報拡散…。お客さまの目は厳しくなり、ただ「家を建てられる」というだけでは、選ばれない時代です。そんな中、工務店が持続的に選ばれ続けるために必要なもの・・・それが「ブランディング」です。そして、ブランディングを根幹から支えるものこそが「クレド(信条)」です。
「クレド(Credo)」とは、ラテン語で「信条」「志」「約束」を意味する言葉です。会社の価値観や使命、行動指針を簡潔にまとめたものが「クレド」です。有名な事例でいえば、アメリカの製薬会社ジョンソン・エンド・ジョンソンの「Our Credo」が有名です。彼らのクレドには「顧客第一主義」「スタッフへの敬意」「地域社会への貢献」などが明記され、経営判断に迷ったとき、必ず立ち戻る「心の羅針盤」として機能しています。つまり、クレドは単なる社内用のスローガンではなく、全スタッフが共有し、日々の行動を律する「企業文化の核」なのです。

工務店にこそクレドが必要な理由
工務店の業務は、単なるモノ売りではありません。お客さまの人生に深く関わり、未来を形にする、極めて信頼性の高い仕事です。ここにクレドが必要な理由は、次の3つに集約されます。
1.「軸」を持たない工務店は、価格競争に巻き込まれる
もし自社の強みやポリシーが曖昧なままだと、どうなるでしょうか?結局は「価格が安いか」「建てるスピードが速いか」といった外的要素だけで勝負することになります。しかし、クレドを持つことで、「私たちはこういう想いで家づくりをしている」という、価格以外の価値基準を明確に打ち出すことができます。お客さまも、単なる安さではなく、共感できる理念を求めています。クレドは、そんなお客さまとの「感情的なつながり」を生むきっかけとなるのです。
2.スタッフ全員が「同じ方向」を向ける
住宅建築は、営業、設計、現場監督、大工、インテリアコーディネーター…多くの人が関わるチームプレーです。しかし、チームに共通の価値観がなければ、サービスの質はバラバラになります。クレドを明文化し、日常的に共有することで、「自分たちはどのような姿勢でお客さまに向き合うべきか」をスタッフ一人ひとりが意識できるようになります。属人的な「できる人頼り」の運営ではなく、組織全体の底上げができます。
3.「ストーリー」でブランドを築く人は「物語」に心を動かされます
スペックや数値よりも、想いや背景に共感して商品を選びます。クレドは、工務店が「どんな想いで家を建てているのか」というストーリーを象徴するものです。このストーリーがあれば、広告も採用活動も、ファンづくりも、すべてが強く、一貫性を持ったものになります。

クレドを作る際に押さえるべきポイント
1.トップ自らの言葉で作る
クレドは、社長や経営者自身の想いから生まれるべきです。外部コンサルタント任せや、スタッフの寄せ集めでは、心に響くクレドはできません。なぜこの仕事をしているのか、どんな家を建てたいのか・・・心の底から湧き上がる言葉を、真剣に紡ぎ出すことが重要です。
2.短く、シンプルに
クレドは覚えやすくなければ意味がありません。「顧客第一」「誠実な家づくり」「地域社会への貢献」など、短い言葉で要点をまとめるべきです。また、難解な言葉や、飾った表現は避けましょう。小学生でもわかる言葉で書くことで、社内外に伝わりやすくなります。
3.日常の中で活かす
作っただけのクレドは、すぐに形骸化します。クレドは、クレドミーティング、定期的な振り返り、スタッフ評価の基準など、日常業務に組み込むことが大切です。「自分たちのクレドに照らして、今日はどうだったか?」常に問い続けることで、クレドは生きた文化になっていきます。

成功している工務店は、必ずクレドを持っている
実際に、地域で強いブランドを築いている工務店の多くは、大小問わず、独自のクレド(理念)を持ち、それを徹底しています。たとえば、「私たちは一軒一軒、家族の未来を背負っていると考えています」、「手間を惜しまない施工こそが、信頼の礎だと信じています」、「地域に根ざし、百年先も愛される家を作ります」・・・このような信条をスタッフ全員が体現しているからこそ、お客さまに圧倒的な信頼を勝ち取っているのです。
これからの工務店にとって、クレドは単なる飾りではありません。ブランディングの「魂」そのものです。競合が価格競争に明け暮れる中で、自社だけの「想い」と「価値観」を堂々と打ち出すことができれば、価格に頼らない、本物のファンを育てることができます。そしてそのファンが、また新たなファンを呼び、ブランドは強く育っていきます。本気で選ばれ続ける工務店を目指すなら、まずはクレドを作り、育てることから始めましょう。
